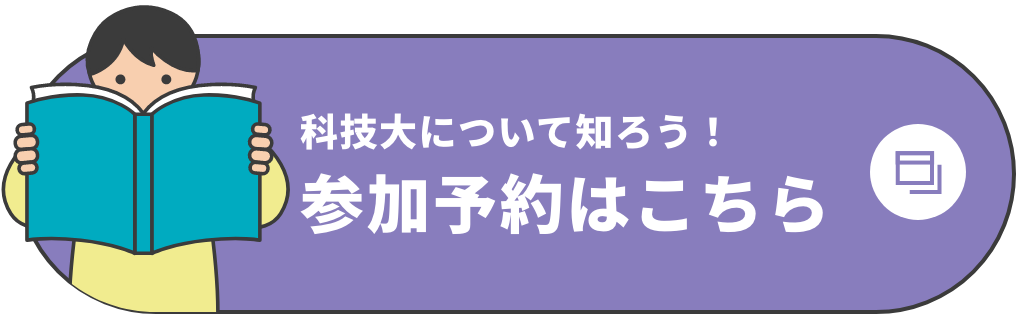模擬講義
応用化学生物学科
デジタル時代における 日本の課題と可能性:物質・材料開発が示す未来
教授・博士(学術) 坂井 賢一AIやデジタル技術が注目される今の時代ですが、日本には、これまでに「物質」や「材料」を生み出す分野で高い実績と独自の強みがあります。なかでも有機化合物は、医薬品やプラスチックなど幅広い分野で活用されており、私たちの生活に深く関わっています。この講演では、蛍光色素を例に、有機化合物が身近なところでどのように使われているかを紹介しながら、材料開発が未来の社会とどのようにつながっていくのかをわかりやすくお話しします。簡単な実験デモも交え、化学の面白さや奥深さを感じていただける内容です。
電子光工学科
植物の成長を計測する技術開発
教授・博士(工学) 七夕 高也植物は、自分の置かれた環境にうまく適応しながら、生きていくためのさまざまなしくみをもっています。こうした植物の機能を解き明かすためには、植物をいろいろな環境で育て、草丈の変化や花が咲くタイミングなど、成長の過程で起こるさまざまなことを、計測することが必要です。しかし、多くの植物を育て、ひとつひとつ計測することは、とても手間がかかる作業です。そこで、植物の成長を自動で、効率よく、しかも詳しく計測するための技術開発が重要です。この講義では、これまでの研究を紹介しながら、植物の成長を計測する技術開発の面白さや難しさ、どのような技術が使われているかなどを紹介したいと思います。
情報システム工学科
スマートフォンでIoTを体感
教授・博士(工学)福田 浩IoT(Internet of Things)により、あらゆるものがインターネットで互いに接続される時代になってきています。無線・有線ネットワークを通じ、身近な家電製品や日頃身に着けている腕時計などに設置されたセンサの情報を収集し、小さなマイクロコントローラ(マイコン)で情報処理したデータがスマートフォンなどの情報機器に届くことで、我々の生活環境や健康状態などを理解し、より快適で豊かな生活を支える仕組みです。本講義ではこのIoT技術に関し、一例としてマイコンとセンサ、スマートフォンを用いて実現する仕組みを説明します。また実際にデモンストレーションを行い仕組みの理解を深めます。
体験系模擬講義
見て触れて学ぶ光ファイバ通信
電子光工学科 准教授・博士(理工学) 小田 久哉AIやビックデータといった現在の最先端の技術を支える要素技術に光ファイバ通信があります。光ファイバ通信は我々の身近な生活においても大容量の情報を短時間に遠くまで届けることが出来るようになり、スマホで高精細な動画が見られるようになりました。光ファイバ通信技術は日進月歩進化していますが、本模擬講義では光ファイバ通信の基礎を講義と簡単な実験を通して学びます。
(※第1回オープンキャンパスで実施したものと同じ内容になります。)
未来のセンサ技術体験 ~柔らかいセンサ~
電子光工学科 准教授・博士(工学) 春田 牧人折り曲げられる、肌に貼れる、やわらかい素材でできた “フレキシブルセンサ”。
医療、スポーツ、ロボットなど、私たちの生活の様々な場面で活用されている未来のセンサ技術を、講義と体験を通して学びます。本イベントでは、大学で行われている研究の一端をわかりやすく紹介するとともに、簡単なフレキシブルセンサの作製体験も行います。理工系の学びや最先端技術に興味がある高校生におすすめです。
レベル別プログラミング教室
-enjoy programming ♫-
共通教育科 准教授・博士(理工学) 石田 雪也高校の指導要領が変わり情報Ⅰが必修科目となり、共通テストでも情報Ⅰが新たに試験に加わりました。大学でのプログラミングの授業は、反転学習、グループワークを用いて行われています。本講義では大学で行われるプログラミング授業を体験していただきます。当日は、高校等でプログラミングの授業を経験した生徒さんと未経験の生徒さんで内容を変更しますので、プログラミング未経験の生徒さんも気軽に参加ください。※会場で経験者、未経験者に分かれて着席いただきます。
特別講義
半導体への誘い
シリコンリサーチ副センター長教授・博士(工学) 山田 崇史
多くの身近な製品に必要不可欠となっている半導体について、実験を交えながら講義します。はじめに金属と半導体の実物を見ながら、その違いを目と手で確認します。半導体の動作は目で見ることが難しいため、仮想空間を利用して実験を進めます。具体的には、講義参加者自らスマートフォンでクイズに答えたり、Web上に作成した簡単な回路に触れたりすることで、さらに理解を深めます。締めくくりとして、計算や記憶、通信などに利用するデモンストレーションをご紹介します。

研究室紹介
応用化学生物学科
カートハウス研究室
プラスチックは低価格、軽量、多用途かつ耐久性のメリットがあります。しかしこれらの海洋プラスチックやマイクロプラスチックは環境問題を引き起こしています。当研究室では、合成プラスチックの代替として、キチンなどの天然資源由来の材料を合成・分析し、その生分解性を分析しています。
木村研究室
本研究室では、医学・歯学・工学を融合し、歯・骨・軟骨・心臓・血管の評価技術や、食品・材料・マイクロプラスチックスの分析技術を開発しています。多分野の専門家と連携し、水中・地上から宇宙までを視野に入れた革新的研究を推進中です。電子光工学科
小田(尚)研究室
人間支援を目的とした各種ロボットのモーションコントロールやロボットビジョンに関する研究を行っています。二足歩行ロボット、移動型ロボット、ロボットアームやロボットハンドなどの取り組みをご紹介します。
横井研究室
本研究室では、主にレーザ光を利用した生体医用計測などに関する研究を行っています。当日は、まず本研究で行っている研究の概要をスライドを用いて簡単に紹介した上で、実際に研究で使用している装置の一部を見学していただく予定です。情報システム工学科
小林研究室
人間工学を基盤として、製品、情報システム、サービスのUI(ユーザインタフェース)の研究・開発をしています。今回のオープンキャンパスでは、千歳市に導入される自動運転バスの外向けヒューマン・マシン・インタフェースの効果的な利用方法と周囲のドライバーに及ぼす影響を検証するVR環境を体験していただきます。また、創造性を発揮できるバーチャルオフィス環境なども体験できます。小松川研究室
本研究室では、AIを活用したシステム研究をしています。例えば、3次元の実空間上にAIアバターを登場させ、人とAIが対話する環境で、如何に人間らしく振る舞えるかといった基礎研究から、医療現場でどのようなサービス(心肺蘇生の訓練)を創れるかなどの応用研究をしています。
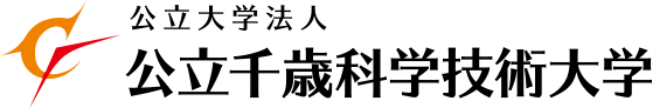




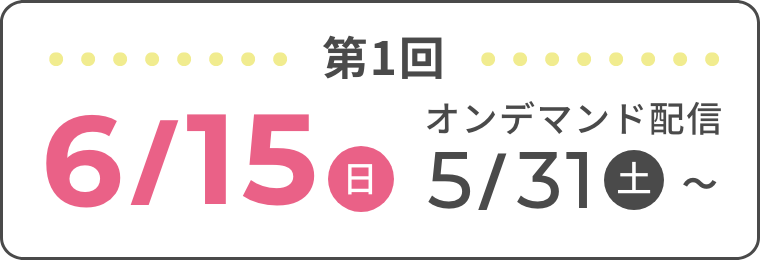


 参加予約はこちら
参加予約はこちら