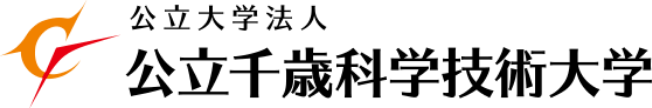情報システム工学科 カリキュラム
カリキュラムの特色
社会で通用するチームワーク、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力などが身に付くプロジェクト系科目が「考える力」を育みます。

カリキュラムは、グローバル社会の技術リーダーとして必要な知識や経験を、自らの体験を通して習得できるように構成されています。
中でも2・3年次にわたって展開するプロジェクト系科目は、地域や環境問題に取り組む、本学科のメインとなる科目です。
少人数のチーム形式で目標達成のために検討を進め、PDCA(Plan-Do-Check-Action)の過程を体験して問題解決を図ることを学習の柱にしています。
情報通信・ICTソリューション・サービスのテーマに取り組む中で、開発の考え方や進め方などを体験し、社会人として欠かせない基礎力を高めます。
また、本学科の専門分野である情報・通信の技術系科目だけでなく、論理的思考力や文章技法、積極性やコミュニケーション能力などを養う科目も用意され、社会で求められるイノベーションを実現できる次世代の技術者に必要な総合力を養います。
中でも2・3年次にわたって展開するプロジェクト系科目は、地域や環境問題に取り組む、本学科のメインとなる科目です。
少人数のチーム形式で目標達成のために検討を進め、PDCA(Plan-Do-Check-Action)の過程を体験して問題解決を図ることを学習の柱にしています。
情報通信・ICTソリューション・サービスのテーマに取り組む中で、開発の考え方や進め方などを体験し、社会人として欠かせない基礎力を高めます。
また、本学科の専門分野である情報・通信の技術系科目だけでなく、論理的思考力や文章技法、積極性やコミュニケーション能力などを養う科目も用意され、社会で求められるイノベーションを実現できる次世代の技術者に必要な総合力を養います。
履修科目の紹介
●必修科目 ◆選択必修科目 ■選択科目
2年次
学びの目標
基礎的な内容を学ぶとともに、プロジェクトの取り組み方も修得共通
●Javaプログラミング ●情報通信システム概論 ●プロジェクト基礎演習 ●AIアルゴリズムとプログラミング
●サービス科学 ●離散数学 ●統計学基礎 ●電子回路実習
■線形代数学II ■情報セキュリティ ■情報基礎学 ■文章技法 ■フーリエ応用
●サービス科学 ●離散数学 ●統計学基礎 ●電子回路実習
■線形代数学II ■情報セキュリティ ■情報基礎学 ■文章技法 ■フーリエ応用
3年次
学びの目標
各分野の専門的な知識を身に付け、より高度なプロジェクトに挑戦情報通信応用分野
●コンピュータネットワーク ■センサネットワーク ■情報通信ネットワーク工学 ■ワイヤレスネットワーク
ICTソリューション分野
●情報システム開発基礎演習 ■AIと機械学習A・B ■データベース工学 ■ソフトウェアデザイン
サービス分野
■ユーザビリティ工学 ■サービスデザイン ■感性工学 ■ユーザインターフェース
共通
●情報システム工学演習 ●情報システムプロジェクト
■代数学概論 ■統計解析 ■計算基礎論 ■コンピュータアーキテクチャ ■幾何学概論
■数値計算概論 ■代数学I ■企業リテラシ ■クラウドコンピューティング ■インターンシップ
■代数学概論 ■統計解析 ■計算基礎論 ■コンピュータアーキテクチャ ■幾何学概論
■数値計算概論 ■代数学I ■企業リテラシ ■クラウドコンピューティング ■インターンシップ
4年次
学びの目標
自分なりの目標を立てて研究に取り組む共通
●情報システムセミナー ●輪講 ●卒業研究A・B
■複素関数と特殊関数 ■幾何学I ■幾何学I演習 ■情報と職業 ■教育とコンピュータ
■複素関数と特殊関数 ■幾何学I ■幾何学I演習 ■情報と職業 ■教育とコンピュータ
科目 PICK UP
サービス科学 (2年次)
サービス科学という学問分野におけるサービス・イノベーションの概念を理解した上で、サービスを改善する際の課題の抽出方法、解決へのアプローチ方法を学びます。さらに情報システムを介して有効活用する上での問題点と注意点、手順について深く学びます。
情報システム工学演習(3年次)
まずハードウェアの面から学修をスタート。センサを用いた情報収集システムの構築スキルを身につけます。その上で次にソフトウェアの領域に挑戦。千歳市の観光課題の解消もしくはVRやUnityを使った新たな企画の立案に取り組みます
情報システム開発基礎演習(3年次)
ソフトウェア工学の柱となる技法として、「ソフトウェア設計に関わるマネジメント方略や設計技法」「データベース技法」「ネットワーク関連及びサーバ構築技法」「AI・ビックデータを活用したデータ活用技法」についてそれぞれ学びます。